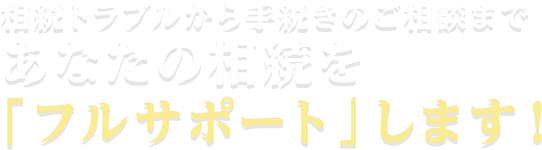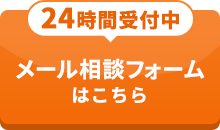解決事例一覧
相続問題の解決事例「同じような悩み」を抱えた方が、どう解決したか
「自分と似たような相続問題は、実際にどう解決されているの?」
「弁護士に依頼すると、本当に問題は解決するの?」
「どのくらいの期間で、どんな結果が得られるの?」
「費用はどのくらいかかるの?」
相続問題は、一つとして同じケースはありません。しかし、多くの方が直面する「典型的な問題」や「よくあるトラブルのパターン」は存在します。
このページでは、宇都宮東法律事務所が実際に解決した相続問題の事例をご紹介します。
守秘義務の観点から、個人を特定できないよう内容を一部変更していますが、問題の本質や解決までのプロセスは実際の事例に基づいています。
事例から学べること
- ・自分と似た状況の人が、どう問題を解決したか
- ・弁護士がどのようにサポートしたか
- ・解決までにどのくらいの期間がかかったか
- ・どのような結果が得られたか
こんな方に特にお読みいただきたい
- ・弁護士に相談すべきか迷っている方
- ・自分の問題が解決可能か不安な方
- ・解決までの流れをイメージしたい方
- ・同じような悩みを持つ方の体験を知りたい方
相続問題は、一人で抱え込んでも解決しません。適切な専門家のサポートがあれば、多くの問題は円満に、または納得できる形で解決できます。
遺産範囲における問題が生じた状況から、円満な遺産分割協議に至るまでの事例
- 亡くなられた方
- 父親、母親
- 相続人
- 長女、長男
- 相続(遺産)
- 不動産、預貯金、現金
1. 事例の概要
1 亡くなられた方
父親、母親
2 相続人
長女、長男
3 相続(遺産)
不動産、預貯金、現金
ご依頼の背景
依頼者である夫婦(長男夫婦)は、父母の世話をするために一緒に暮らしていました。
この同居期間は約10年間続いており、その間、依頼者夫婦は父母の日常的な介護や生活支援を行っていました。
ある時、父母が相次いで亡くなり、遺産分割が必要となりました。父が亡くなってから約3ヶ月後に母も亡くなったため、両親の相続手続きを同時に進めることになりました。
依頼者は遠方で生活する長女にこれまでの経緯を説明しました。
しかし、長女は依頼者が生前の遺産を引き出していたことから遺産範囲について疑問を持ち、遺産分割が進まない状態となりました。
具体的には、以下のような点が問題となりました:
- 父母の生前の預金通帳に記録されている引き出し
- 父母の介護にかかった費用の取り扱い
- 依頼者夫婦が同居していた家屋の評価
- 父母が所有していた株式や保険の取り扱い
これらの問題により、相続人間で遺産の範囲や金額について共通の認識を持つことができず、遺産分割協議が難航していました。
依頼人の主張
依頼者は、以下のような主張を行っていました:
- 預金の引き出しについて:
父母の日常生活費や医療費、介護費用のために使用したものであり、不当な使い込みではない。 - 介護費用について:
長年にわたる介護の負担を考慮すべきであり、それに見合う対価を認めてほしい。 - 同居していた家屋について:
固定資産税評価額ではなく、実際の市場価値で評価すべきである。 - 株式や保険について:
これらも遺産に含めるべきであり、適正に評価して分割の対象とすべきである。 - 遺産分割の方法について:
法定相続分に基づいて遺産分割を行いたい。
しかし、長女が感情的であり、訴訟外の話し合いが難しいため、依頼者は弁護士や裁判所を介して話し合いを進めていくことを希望していました。
サポートの流れ
この事例における弁護士のサポートは、以下のような流れで進められました:
- 事実関係の整理:
依頼者から詳細な事情聴取を行い、遺産の内容、これまでの経緯、問題点などを整理しました。 - 証拠の収集:
預金通帳のコピー、介護記録、医療費の領収書、不動産の評価資料など、必要な証拠を可能な限り収集しました。 - 長女への連絡:
依頼者の代理人として、長女に対して書面で連絡を取り、話し合いの機会を設けることを提案しました。 - 資料の開示:
収集した証拠資料を整理し、長女側に開示しました。特に、過去の預金の引き出しに関する資料を詳細に提示しました。 - 調停の申立て:
当事者間での直接の話し合いが困難であったため、家庭裁判所に調停を申し立てました。 - 調停での交渉:
調停の場で、双方の主張を整理し、中立的な調停委員を交えて解決策を模索しました。 - 和解案の提示:
調停の過程で、双方が受け入れ可能な和解案を作成し、提示しました。
このプロセスを通じて、弁護士は依頼者の利益を守りつつ、公平で合理的な解決策を見出すことに注力しました。
結果
長女は、最初は納得しようとしなかったものの、依頼者が丁寧に証拠を収集し、開示していくことで次第に状況が変化しました。
具体的には以下のような進展がありました:
- 預金の引き出しに関する理解:
通帳の記録と照らし合わせて、引き出された金額が父母の生活費や医療費に相当することが明らかになりました。 - 介護の評価:
依頼者夫婦による長年の介護の実態が明らかになり、その労力と負担が適切に評価されました。 - 不動産の評価:
中立的な不動産鑑定士による評価を行い、公平な価格が算定されました。 - 株式や保険の取り扱い:
これらも遺産に含めることで合意し、適正な評価額が算出されました。
この結果、依頼者と長女は遺産の範囲について共通の認識を持つことができ、円満な遺産分割協議が実現しました。
特筆すべき点として、依頼者が長年父母を献身的に支えてきたことに対して、長女から感謝の言葉が述べられるようになりました。
これは、調停の過程で依頼者の介護の実態が詳細に明らかになったことが大きく影響しています。
最終的に、双方が法定相続分に基づく遺産分割で合意し、調停が成立しました。
具体的な分割の内容は以下の通りです:
- 不動産:長男(依頼者)が取得し、長女に対して代償金を支払う
- 預貯金:法定相続分に基づいて分割
- 現金:法定相続分に基づいて分割
- 株式:換金して法定相続分に基づいて分割
- 保険金:法定相続分に基づいて分割
また、依頼者の介護労力に対する評価として、遺産の一部を特別受益として認めることで合意しました。
事例から学ぶ教訓
この事例から、遺産分割問題に対する適切な解決策として、以下のような教訓を得ることができます:
- 弁護士の活用:
感情的対立がある場合、弁護士を介することで冷静な話し合いが可能になります。 - 裁判所の利用:
調停など、裁判所の制度を利用することで、中立的な立場からの解決が図れます。 - 証拠の重要性:
預金の引き出しや介護の実態など、客観的な証拠を示すことが問題解決の鍵となります。 - 丁寧な説明:
相手方が納得するまで、根気強く丁寧に説明することが重要です。 - 感情面への配慮:
法的な側面だけでなく、相続人間の感情的な和解も重要です。 - 専門家の活用:
不動産鑑定士など、必要に応じて専門家の意見を取り入れることで、公平な解決が図れます。 - 柔軟な解決策:
法定相続分にこだわらず、各相続人の事情を考慮した柔軟な解決策を模索することも有効です。
まとめ
本事例は、当初は遺産の範囲をめぐって対立していた相続人が、適切な手続きと丁寧な説明を通じて和解に至った好例といえます。
遺産分割の問題は単なる財産の分配以上に、家族の歴史や感情が複雑に絡み合う難しい問題です。
しかし、本事例のように、客観的な証拠の提示と冷静な話し合いの場を設けることで、多くの場合は円満な解決に至ることができます。
相続人それぞれの立場や思いを尊重しつつ、公平で合理的な解決策を見出すことが重要です。
遺産分割で問題が生じた場合は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをお勧めします。
弁護士などの専門家のサポートを得ることで、複雑な問題も円滑に解決できる可能性が高まります。
故人の死後、腹違いの兄弟が存在することが判明し、遺産分割協議が迅速に成立した事例
- 亡くなられた方
- 母
- 相続人
- 長男、長女、次男
- 相続(遺産)
- 預貯金、不動産、車
亡くなられた方
この事例の中心となるのは、亡くなったお母様です。お母様は生前、長男から世話を受けていたようです。しかし、お母様の死後、遺産相続の手続きを進める中で、腹違いの兄弟が1人存在することが明らかになりました。このような突発的な事実の発覚が、遺産分割問題の複雑さを増す要因となったのでしょう。
相続人
当初、相続人は長男、長女、次男の3人だと思われていました。しかし、お母様の死後、腹違いの兄弟が1人存在することが判明しました。この兄弟は、他の相続人にとって、存在自体が驚きだったようです。このような予期せぬ相続人の存在が、遺産分割の難しさを増幅させることになります。
相続(遺産)
相続の対象となる遺産は、預貯金、不動産、車でした。特に、不動産と車をめぐっては、依頼者である長男と、新たに発覚した腹違いの兄弟との間で、利害関係が対立することになります。
ご依頼の背景
依頼者である長男は、お母様が亡くなった後、遺産相続の手続きを進めていました。その過程で、腹違いの兄弟が1人存在することが明らかになったのです。
しかし、その兄弟との連絡が難しい状況でした。連絡が取れないということは、遺産分割交渉を進める上で大きな障害となります。
そこで、依頼者は弁護士に助けを求めたのでしょう。
依頼者の主張は明確でした。生前、お母様の世話をしていたことから、不動産と自動車は自分が取得したいというものです。また、お母様の死後に立て替えた自動車税と固定資産税は、遺産から精算してほしいとの要望もありました。
このような依頼者の主張を踏まえ、弁護士は遺産分割交渉に臨むことになります。
弁護士は、まず腹違いの兄弟に関して所在調査を行いました。相続人全員の住所を特定することが、交渉の第一歩だったのです。住所が判明した後、弁護士は迅速に遺産分割交渉を開始しました。
交渉の結果、腹違いの兄弟も、自分以外に兄弟がいることに驚いていたことが分かりました。突然の相続人の出現は、当事者全員にとって驚きだったのでしょう。
しかし、弁護士を代理人に立てたことで、両者の代理人間での交渉が円滑に進められました。法律の専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な議論が可能になったのです。
遺産に含まれる自動車の価値については、当初争いがありました。しかし、弁護士が提出した資料に基づき、価値が算定されました。
客観的な資料に基づく価値の算定は、争いを避ける上で有効だったのでしょう。
その結果、不動産と自動車は依頼者が取得する形で、遺産分割協議が成立しました。また、固定資産税と自動車税についても、遺産から清算することで合意が得られました。
この事例から学ぶべきことは、遺産相続においては、予期せぬ事態が起こりうるということです。今回は、腹違いの兄弟の存在が突如として明らかになりました。このような状況下でも、適切なサポートと効率的な交渉によって、迅速かつ円滑に遺産分割協議を進めることができたのです。
遺産分割問題は、法律的にも感情的にも複雑なものです。予期せぬ相続人の存在は、問題をさらに難しくするでしょう。しかし、弁護士などの専門家の助言を求めることで、解決への道筋が見えてくるはずです。
また、客観的な資料に基づく議論や、代理人間での冷静な交渉は、争いを避ける上で有効です。感情的な対立に陥ることなく、合理的な解決を目指すことが重要だと言えます。
遺産分割問題に直面した際は、一人で抱え込まずに、専門家のサポートを受けることをおすすめします。適切な助言と効率的な交渉によって、たとえ予期せぬ事態が起きても、円滑な遺産分割が実現できるでしょう。
遺産相続は、法律だけでなく、家族の感情も絡む複雑な問題です。しかし、専門家の力を借りながら、一歩一歩前に進んでいくことが大切なのではないでしょうか。
長期間音信不通状態だった相続人と迅速に遺産分割協議がまとまった事例
- 亡くなられた方
- 母
- 相続人
- 夫、長男、長女
- 相続(遺産)
- 預貯金
亡くなられた方
母親が亡くなられたことがこの事例の発端となりました。母親は家族の中心的存在であり、その死去は残された家族にとって大きな悲しみであったに違いありません。しかし、悲しみに暮れる間もなく、相続手続きという現実的な問題に直面することになったのです。
相続人
相続人は、夫、長男、長女の3人でした。夫は妻を亡くした悲しみを抱えながらも、長男とともに相続手続きを進めようとしていました。しかし、長女との関係が良好でなかったため、手続きは難航することになります。長女は若い頃に家を出た後、音信不通の状態が続いていたのです。
相続(遺産)
母親が残した遺産は預貯金でした。金額の詳細は明らかにされていませんが、相続人にとって無視できない額であったことは想像に難くありません。この預貯金をめぐって、相続人間で遺産分割協議を行う必要がありました。
ご依頼の背景
依頼人である夫と長男は、長女との関係悪化から、母親の遺産に関する相続手続きを進めることができずにいました。長女は他の相続人との関係が良好でなく、若い頃に家を出た後、音信不通の状況が続いていたのです。このような状況下で、依頼人は弁護士に相談し、問題解決を図ろうとしたのでした。
依頼人の主張は明確でした。法定相続分に基づいて、できるだけ早く遺産分割協議を成立させたいというものです。遺産分割に関する紛争は、時間が経過するほど解決が難しくなります。依頼人は、早期解決を望んでいたのでしょう。
弁護士は、まず長女の所在調査を実施しました。長期間行方不明だった彼女の住所を特定することが、問題解決の第一歩だったのです。住所が判明した後、弁護士は速やかに遺産分割交渉に取りかかりました。
依頼人は、長女との直接の連絡を望んでいませんでした。おそらく、感情的な対立を避けたいと考えたのでしょう。そこで、弁護士が代わりに長女との連絡を取ることになりました。
弁護士は、故人の経緯や詳細な事情も含めた説明を長女に行いました。遺産分割においては、故人の意思を尊重することが重要です。故人の経緯を丁寧に説明することで、長女の理解を得ることができたのでしょう。
その結果、長女は法定相続分に基づく分割に同意しました。法定相続分は、民法で定められた相続分のことです。今回のケースでは、夫が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1ずつを相続することになったはずです。
長女の同意が得られたことで、遺産分割協議は迅速に成立することができました。弁護士の働きかけがなければ、長期化する可能性もあったでしょう。
遺産分割協議が成立した後は、預金解約手続きが必要になります。弁護士は、この手続きのサポートも行いました。相続人全員の同意を得た上で、預金を解約し、相続人に分配する必要があります。
依頼から預金解約までの期間はわずか6ヶ月でした。通常、相続手続きには数ヶ月から1年以上かかることもあります。それを考えると、今回の事例は非常にスムーズに解決したと言えるでしょう。
この事例から学ぶべきことは、遺産分割交渉を円滑に進めるためには、適切な説明や話し合いが重要だということです。当事者同士の感情的な対立が障害となることもあります。そのような場合、弁護士などの専門家に相談することが効果的です。
今回は、弁護士が交渉の役割を担うことで、無事に協議成立へとたどり着くことができました。長期間音信不通の状態にあった相続人との遺産分割協議が、わずか6ヶ月で迅速にまとまったのは、弁護士の尽力があったからこそでしょう。
相続問題は、法律的な問題であると同時に、感情的な問題でもあります。適切な専門家のサポートを得ることで、円滑な解決を目指すことが重要だと言えます。
素人による遺産分割協議書作成で不備があり、長期間不動産名義変更ができなかった事例
- 亡くなられた方
- 父、母
- 相続人
- 長女の子2名、長男、養子
- 相続(遺産)
- 不動産
亡くなられた方
この事例では、父と母の両方が亡くなられたことが、相続問題の発端となりました。親の死去は、子供にとって大きな悲しみであり、同時に、相続という現実的な問題に直面することになります。
相続人
相続人は、長女の子2名、長男、そして養子の4人でした。養子は依頼人の元妻であり、他の相続人との関係性に問題を抱えていました。このような複雑な家族関係が、遺産分割を難しくする要因の一つとなったのでしょう。
相続(遺産)
相続の対象となる遺産は、不動産でした。不動産は、家族にとって重要な資産であり、その分割や名義変更をめぐって、相続人間で意見が対立することも珍しくありません。
ご依頼の背景
依頼人は、故人の名義である不動産と預貯金について、死亡後に専門家を通さずに遺産分割協議書を作成したそうです。しかし、その協議書には記載内容に不備があり、不動産の名義変更ができない状態が長期間続いていました。
また、養子は依頼人の元妻であり、話し合いが難航する状況となっていました。家族関係の問題が、遺産分割を一層複雑にしていたのです。
依頼人の主張は明確でした。故人が亡くなった後、長期間にわたって不動産を管理しており、名義変更を迅速に行いたいというものです。不動産の名義変更が遅れることで、様々な不都合が生じる可能性があります。依頼人の焦りは理解できるものでした。
弁護士は、まず養子の所在調査を実施しました。養子の住所が特定できなかったため、現住所を把握することが、交渉の第一歩だったのです。住所が判明した後、弁護士は養子との交渉を開始しました。
養子との間には感情のもつれも存在していました。遺産分割交渉では、法律的な問題だけでなく、感情的な問題にも対処する必要があります。弁護士は、粘り強い交渉を続けた結果、養子から不動産名義変更への協力を取り付けることができました。
その後、弁護士は新たに不動産のみを対象とした遺産分割協議書を作成しました。最初の協議書には不備があったため、改めて作成する必要があったのです。新たな協議書のもと、遺産分割協議は成立し、不動産の名義変更も無事に完了しました。
この事例から学ぶべきことは、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼することが重要だということです。素人が作成した協議書には、法的な不備が存在する可能性があります。そのような不備が、後々の手続きを困難にすることもあるのです。
また、遺産分割交渉が難航する場合でも、適切な方法で交渉を進めることで解決が可能であることが分かります。今回は、弁護士の粘り強い交渉が、問題解決の鍵となりました。
遺産相続に関する問題は、法律的にも感情的にも複雑なものです。専門家の支援を受けることで、スムーズな解決を目指すことができるでしょう。遺産分割協議書の作成から、相続人との交渉、そして名義変更手続きまで、弁護士のサポートがあれば、問題解決への道筋が見えてくるはずです。
相続問題に直面した際は、一人で抱え込まずに、専門家に相談することが重要だと言えます。適切な支援を受けることで、円滑な遺産分割と、家族関係の修復が期待できるのではないでしょうか。
迅速な遺産分割成立が実現した家庭裁判所の審判手続きの事例
- 亡くなられた方
- 兄弟(兄)
- 相続人
- 長女、長男、次男の子2名、次女、四男
- 相続(遺産)
- 預貯金
亡くなられた方
この事例の中心となるのは、亡くなった兄弟(兄)です。兄は生前、長女から献身的な支えを受けていました。長期入院中も、病気で苦しむ兄に対して、長女は見舞いを欠かさず行っていたそうです。このような経緯から、兄の死後、長女は遺産分割問題に関わることになりました。
相続人
相続人は、長女、長男、次男の子2名、次女、四男の6人でした。兄弟間には、腹違いの関係もあり、そのため関係が疎遠になっていたようです。このような家族関係の複雑さが、遺産分割を難しくする要因の一つとなったのでしょう。
相続(遺産)
相続の対象となる遺産は、預貯金でした。預貯金は、相続人全員に分配されるべきものですが、遠方に住む相続人や連絡が取れない相続人がいたため、分割の交渉が難航していました。
ご依頼の背景
依頼者である長女は、亡くなった兄を献身的に支えていました。長期入院中も、病気で苦しむ兄に対して見舞いを欠かさず行っていたそうです。このような事情から、兄の死後、長女は遺産分割問題に関わることになりました。
しかし、遺産の預貯金を分割しようと他の相続人に連絡を取っても、腹違いの兄弟間で関係が疎遠であったため、交渉は難航しました。相続人の中には、遠方に住んでいる人や、連絡が取れない人もいたのです。
依頼者の主張は明確でした。法定相続分で取得することに問題はないという立場でしたが、相続人との交渉が難航しているため、早期の解決を望んでいました。遺産分割が長引くことで、様々な不都合が生じる可能性があります。依頼者の焦りは理解できるものでした。
弁護士は、まず相続人の所在調査を行いました。相続人全員の住所を特定することが、交渉の第一歩だったのです。住所が判明した後、弁護士は相続人との交渉を試みました。
しかし、連絡に対して非協力的な態度を示す相続人もいました。遺産分割交渉では、相続人全員の合意が必要です。一部の相続人が非協力的だと、交渉は難航してしまいます。
そこで、弁護士は速やかに調停の申立てを行いました。調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って、当事者同士の話し合いを促進し、合意の成立を目指す手続きです。
調
停の結果、代襲相続人2名だけが協議に参加しました。代襲相続人とは、相続人が亡くなった場合に、その相続人の子供が相続権を引き継ぐことを指します。
調停の場では、依頼者に対する遺産隠匿等の主張がありました。しかし、弁護士が証拠を提示することで、そのような事実はないことが明らかとなり、協議が進められました。
最終的には、出席しない相続人がいたことから、弁護士は迅速に審判への移行を求めました。審判とは、家庭裁判所の裁判官が、調停で合意に至らなかった事項について、裁判所の判断で決定を下す手続きです。
法定相続分で取得する内容で、遺産分割の審判が成立しました。法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。審判では、この法定相続分に基づいて、預貯金が分割されることになったのでしょう。
この事例から学ぶべきことは、家庭裁判所の審判手続きを利用することで、遠方に居住する相続人や連絡が取れない相続人がいる中でも、迅速な遺産分割成立が実現できるということです。
相続人全員の合意を得ることが難しい場合、調停や審判といった家庭裁判所の制度を活用することが有効です。これらの制度を利用することで、遺産分割問題においてスムーズな解決が図られることがわかります。
遺産分割は、法律的にも感情的にも複雑な問題です。相続人間の関係性によっては、話し合いが難航することもあるでしょう。そのような場合、一人で抱え込まずに、弁護士など専門家の助言を求めることが重要です。
また、調停や審判といった家庭裁判所の制度を活用することで、円滑な遺産分割が実現できる可能性があります。遺産分割問題に直面した際は、これらの選択肢も視野に入れながら、解決への道筋を探ってみてはいかがでしょうか。
非協力的な相続人との対話を通じて遺産分割審判手続きを経て有益な遺産分割が実現した事例
- 亡くなられた方
- 義母
- 相続人
- 養子(依頼者)、四男、三男の子(代襲相続人)
- 相続(遺産)
- 不動産、預貯金
亡くなられた方
この事例の中心となるのは、亡くなった義母です。依頼者は、生前に妻と共に義母の世話を行い、妻が亡くなった後も義母と同居して献身的に世話を続けてきたそうです。このような依頼者の献身的な行動が、後の遺産分割問題に大きな影響を与えることになります。
相続人
相続人は、養子(依頼者)、四男、三男の子(代襲相続人)の3人でした。代襲相続人とは、相続人が亡くなった場合に、その相続人の子供が相続権を引き継ぐことを指します。この事例では、三男が既に亡くなっていたため、その子供が代襲相続人となったのです。
相続(遺産)
相続の対象となる遺産は、不動産と預貯金でした。特に、義母名義の自宅をめぐっては、依頼者と代襲相続人との間で利害関係が対立することになります。
ご依頼の背景
依頼者は、義母が亡くなった後、義母名義の自宅に住むことを希望していました。そのために、他の相続人に連絡を取ったそうです。
しかし、疎遠だった三男の子(代襲相続人)が非協力的であり、交渉は難航してしまいました。代襲相続人との関係性の悪さが、遺産分割を困難にする要因となったのです。
そこで、依頼者は弁護士に助けを求めることになりました。
依頼者の主張は明確でした。故人の生前、代襲相続人と交流がなかったにもかかわらず、非協力的な態度を取られることや、そのまま持ち分を主張されることが納得できないというものです。
依頼者の心情は理解できるものでしょう。義母の世話を献身的に行ってきた依頼者にとって、突然現れた代襲相続人の非協力的な態度は受け入れがたいものだったのでしょう。
このような依頼者の主張を踏まえ、弁護士は遺産分割交渉に臨むことになります。
弁護士は、まず協力的な相続人である四男に連絡を取り、協力を求めました。その結果、相続分譲渡証書を取得することができました。相続分譲渡とは、相続人が自分の相続分を他の相続人に譲渡することを指します。
一方、非協力的だった代襲相続人には、郵送や電話で連絡を試みましたが、拒否され続けました。代襲相続人の非協力的な態度は、遺産分割を大きく阻害する要因となったのです。
このような状況下で、弁護士は家庭裁判所による遺産分割調停の申立を迅速に行いました。調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って、当事者同士の話し合いを促進し、合意の成立を目指す手続きです。
調停手続きの結果、相続分譲渡を行った四男には、手続きの途中で脱退してもらうことになりました。家庭裁判所で正式に脱退の手続きが行われたのです。
一方、代襲相続人は調停手続きに参加しなかったため、審判に移行することになりました。審判とは、家庭裁判所の裁判官が、調停で合意に至らなかった事項について、裁判所の判断で決定を下す手続きです。
審判書が届いた後、代襲相続人が初めて協議に応じ、弁護士を代理人に付けました。法律の専門家が介入したことで、ようやく建設的な議論が可能になったのでしょう。
その結果、代理人同士で交渉が行われ、自宅の不動産と預金・貯金を全て依頼者が取得し、低額な解決金を代襲相続人に支払うことで、和解が成立しました。
この事例から学ぶべきことは、遺産分割問題においては、相続人間の対話が重要だということです。今回は、非協力的な相続人の存在が問題を複雑にしましたが、弁護士の助言を得ながら、粘り強く対話を続けることで、最終的には有益な遺産分割が実現したのです。
遺産分割問題は、法律的にも感情的にも複雑なものです。相続人間の関係性によっては、対立が深刻化することもあるでしょう。しかし、専門家の力を借りながら、対話を続けることが問題解決の鍵となります。
また、調停や審判といった家庭裁判所の制度を活用することも有効です。これらの制度は、当事者間の合意形成を促進し、公平な解決を導く上で重要な役割を果たします。
遺産分割問題に直面した際は、一人で抱え込まずに、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な助言を得ながら、相続人間の対話を続けることで、たとえ難しい問題でも解決への道が開けるはずです。
遺産相続は、法律だけでなく、家族の感情も絡む複雑な問題です。しかし、対話を重ね、時には法的な手続きも활用しながら、一歩一歩前に進んでいくことが大切なのではないでしょうか。そうすることで、今回の事例のように、有益な遺産分割が実現できるはずです。
相続放棄の期限がせまり、相続の承認又は放棄の期間伸長申立てを行い、遺産調査後、遺産分割協議をまとめた事例
- 亡くなられた方
- 兄弟(兄)
- 相続人
- 妹、弟、姪2人
- 相続(遺産)
- 不動産、預貯金、火災保険、株式
ご依頼の背景
被相続人は生前配偶者がおらず、直系尊属も不在のため、弟である依頼者が相続人となった。
死亡後2週間以上経過してから相続が開始したことを知り、債務も相当額ある可能性があるという状況であり、相続を承認するか放棄するか判断することが困難な状況であった。
依頼人の主張
突然被相続人が死亡したことを知ったため遺産の詳細が分からず、不安であるとのことであった。
遺産が明らかになった後も調停にはせず交渉を行いたいが、音信不通となっている相続人もいたため、交渉も弁護士に依頼するべきか迷っているとのこと。早急な解決を希望。
サポートの流れ
コロナ禍の影響も考慮し、相続人調査及び遺産調査と並行して家庭裁判所に6カ月の相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てを行った。
各銀行への弁護士会照会やCICへの情報開示請求等の相続財産の調査、当初依頼人が懸念していた多額の負債はないことが判明したため、相続の承認後、遺産分割協議に移行した。
相続人調査ならびに所在調査後、まずは相続人らに連絡文書を送付することで交渉を始めた。
結果
交渉の結果、依頼人の希望どおり、相続財産の預貯金・保険・株式に関しては法定相続分どおり相続するという内容で合意となった。
また、不動産に関しては、不動産会社の査定の結果、評価額はほぼ0円ということ、当初より依頼人は取得を希望していなかったということもあり、評価額ゼロベースで他の相続人が相続することとなった。
以上の内容で、依頼人が金融資産の全てを取得し、代償金をその他の相続人に対し支払うという旨の遺産分割協議書を作成し、代表相続人の代理人として、当職で金融機関の解約と代償金の支払いまで行うことで、早期な解決に至った。
依頼人としては、疎遠となっていた相続人との遺産分割協議への不安や相続財産である不動産の固定資産税の支払いの期日などにより早急な解決を希望していたが、相続放棄期間伸長申立の依頼から医サイン分割協議成立、代償金の支払いまで約1年で円満な解決に至った。
音信不通となっていた相続人への相続分譲渡の交渉後、遺産分割協議をまとめた事例
- 亡くなられた方
- 叔母
- 相続人
- 甥姪14名
- 相続(遺産)
- 不動産、預貯金、現金
ご依頼の背景
依頼人は、生前妻と一緒に被相続人の面倒を見てきたが、代襲相続人が14名おり、その中には音信不通となっている相続人もいた。
また、遺産が1億円以上あり相続税申告が必要な状況であり、早急な対応が求められた。
依頼人の主張
被相続人の生前、交流がなく、依頼人が何度か自宅に行き手紙を残すも連絡のとれない相続人が相続人の中におり、調査を探偵に相談したところ、費用がかなりかさむとのことで遺産分割にあたり窮した状況であった。
それらの相続人には、相続放棄もしくは相続分譲渡をしてもらい、残る相続人たちで法定相続分にそって金融資産を分割したい、自宅不動産は評価額ゼロベースで依頼人が取得するようにしたいとのことで依頼となった。
サポートの流れ
まず音信不通となっていた相続人含め、被相続人の生前、親族付き合いのなかった3名の相続人に対し、依頼人が被相続人の療養看護に努めたことなどの寄与を考慮し、相続分譲渡もしくは相続放棄いただきたいとの交渉を行った。
結果、相続人3名は相続分譲渡に了承し、それぞれ印鑑代を支払うことで相続分を譲渡する旨の相続分譲渡証書を作成した。
そして、残る11名の相続間で遺産分割協議書を作成し、無事遺産分割協議がまとまることとなった。
結果
当初の依頼人の希望どおり、代襲相続人14名のうち3名は相続分を譲渡し、残る11名で法定相続分にそった金融資産の分割を行った。依頼人が金融資産の全てを取得し、代償金としてその他の相続人に対し支払うという内容の遺産分割協議書を作成し、代表相続人の代理人として、当職で金融機関の解約と代償金の支払いまで行うことで、早期な解決に至った。
依頼人とその妻による約4年間の療養看護の寄与分も取得する内容で、その他の相続人から承諾を得ることができ、自宅不動産も評価額ゼロベースで依頼人が取得するということで遺産分割協議を成立させた。
また、代襲相続人14名と相続人が多数であり依頼人としては相続税の申告の期限も懸念されていたものの、当職より電話や書面による連絡を続けることによって、税理士と綿密に連携をしながら相続税申告期限内(ご依頼から約半年)に無事に話し合いで解決するに至った。