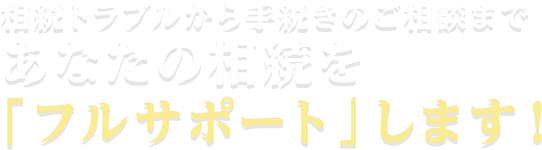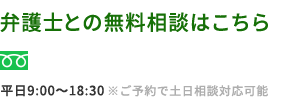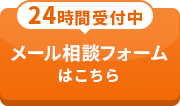空き家にまつわる不動産問題
1 はじめに
私たち宇都宮東法律事務所の注力分野の1つに「相続」があります。
最近相続のご相談で多いのは「遺産のうち不動産があるけれども、だれも取得希望していないのですが・・・」というご相談です。
こういったケースの場合、大体がかなり老朽化した家屋(土地つき)、立地的にも一般ユーザーに需要がない物件であったりと、物件自体に問題があることが多いです。
みなさん、ご相談に来られた際に「相続放棄をしたい」とおっしゃいますが、民法上の「相続放棄」(民法915条)ができないケースもあります。先日ご相談に来所された方の中にも、このような手続きがあること自体知らなかった、というご相談者様もいらっしゃいました。
そこで、今回は「相続放棄」について、最近の判例傾向等についてお話したいと思います。
2 相続放棄の熟慮期間
民法915条1項において「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とされています。これには熟慮期間の定めがあり、起算点について「自己のために相続の開始を知った時」とされています。
空き家を巡る相談で多いのが、被相続人死亡の事実を知っていたし、遺産のうち不動産があることは知っていたが、被相続人とは疎遠であったためそのままにしていたところ、固定資産税の支払いを求める通知書が届いた、だれも取得を希望せず空き家になってしまっている、被相続人の死亡を知ってから既に3か月経過しているが相続放棄できないか?というものです。
このようなケースにおいて、相続放棄は認められるのでしょうか?
3 裁判所の考え方
(1)最高裁
相続放棄の熟慮期間に関する最高裁判決(最判昭59・4・27判時1116・29)は以下の通り判示しています。
「生前被相続人と10年以上にわたり親子としての交流がなく、被相続人の資産及び負債について一切説明を受けたこともなかった相続人らが、被相続人の死亡から約1年後に債権者から連帯保証債務の弁済の請求を受け、当該請求から3か月以内に相続放棄の申述をした事案について、最高裁は、熟慮期間の起算点として、原則として上記大審院判例のとおり、相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知れば足り、遺産の存否の認識は影響がないが、例外的に、相続人が積極・消極の双方にわたり相続の対象となる財産が存在しないと誤信していたために相続放棄の手続をとる必要がないと考えて熟慮期間を徒過した場合には、その誤信につき、過失がないことを条件に、起算日を遺産の認識時又は認識可能時に繰り下げることができる」としました(最判昭59・4・27判時1116・29)」。
本判決の射程は、相続人の相続財産に対する認識が積極・消極ともに存在しないと思っていた場合に限られ、積極財産の存在は認識していたものの消極財産については存在しないと誤信していた場合には当然には及ばないと考えられています。
学説上は①相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた場合に限られるとする見解(現定説)と②一部相続財産の存在は知っていたが通常人がその存在を知っていれば当該相続放棄をしたであろう債務が存在しないと信じた場合も例外的事情に含まれるとする見解(非現定説)に分かれており、最高裁は一貫して限定説を採用しています。
(2)下級審
もっとも下級審の中には非限定説をとっていると思われるものも以下の通り、存在します。
事例:東京高決平12・12・7判タ1051・302
相続放棄申述を却下した原審判に対する即時抗告審において、相続人が、相続の時点で相続開始の事実及び自分が相続人であることを知っていたとしても、自らは被相続人の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間に単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択することは期待できなかったのであるから、被相続人死亡の事実を知ったことによってはいまだ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないとして、原審判を取り消し、放棄申述受理のために差し戻した事例。
事例:名古屋高決平19・6・25家月60・1・97
被相続人Aの子であるBが、Aの死亡を知った当時、Aの遺産として不動産が存在することを認識していたものの、姉であるCが同不動産を相続するものと信じ、かつ、そう信じることにつき相当の理由があり、また、別件訴訟の訴状を受け取るまで相続債務の存在を知らず、かつ、知らなかったことにつき相当の理由があるときは、民法915条1項本文所定の期間は、Bが別件訴訟の訴状を受け取って相続債務の存在を認識した時から起算すべきである。
事例:東京高決平19・8・10家月60・1・102
熟慮期間を徒過しているとして、相続放棄の申述を却下した原審判に対する抗告審において、被相続人に相続財産が全く存在しないと相続人が誤信した場合だけでなく、被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも、民法915条1項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当であるとして、原審判が取り消され、相続放棄の申述が受理された事例。
4 最近の裁判例の傾向について
家庭裁判所における相続放棄の申述の受理自体は広く受理を認める傾向にあるといわれています。これは家庭裁判所は一応の審理をすれば足りるとか、却下すべきことが明白でない限り受理をすべきであるなどの高裁決定(福岡高決平成2・9・25判タ742・159、東京高決平22・8.10家月63・4.129)があることとも関連しているように思われます。
しかし、このことと、受理されたとしても、相続放棄の有効性は別途訴訟等で判断されることは別のことになります。
最近、法定相続人らが相続放棄の各申述をした事案において、各申述の遅れは、相続放棄手続きがすでに完了したとの誤解や被相続人の財産についての情報不足に起因しており、法定相続人らの年齢や被相続人との関係からしてやむを得ない面があったというべきであるから、本件における民法915条1項所定の熟慮期間は、法定相続人らが相続放棄手続きや被相続人の財産に関する説明を受けた時期から進行するとして、熟慮期間を経過しているとして申述を却下した原審判を取り消し、各申述を受理する決定が出ました(東京高裁令1・11・25決定)。
この中でも「なお、付言するに、相続放棄の申述は、これが受理されても相続放棄の実体要件が具備されていることを確定させるものではない一方、これを却下した場合は、民法938条の要件を欠き、相続放棄したことがおよそ主張できなくなることに鑑みれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合を除き、相続放棄の申述を受理するのが相当」と示されています。
5 最後に
以上の通り、最近では積極財産の存在を認識していても、事情によっては、相続放棄自体は家庭裁判所において広く受理される傾向にあるといえます。このため、このようなケースでもあきらめずに専門家にご相談いただくことが重要と思います。
相続放棄が難しい場合でも、弁護士に依頼すれば空き家についての遺産分割協議や、負債が多額の場合には破産等含め債務整理をすることでトラブルを解決することが可能です。
当事務所でも随時ご相談を実施しておりますので、お困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。