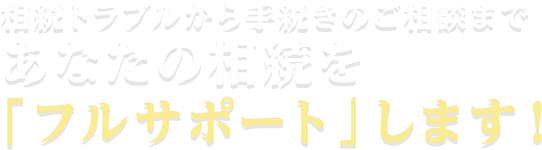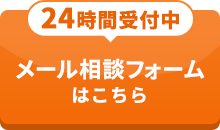遺産の使い込みを疑われた場合の適切な対処法
はじめに
相続が発生したときによく発生する相続人間のトラブルとして、被相続人と同居していた相続人の一人が遺産を使い込んだのではないかと他の相続人から指摘がされることがあります。
本コラムでは、遺産の使い込みに身に覚えがないのにもかかわらず疑われてしまった場合の適切な対処法について、法的観点と実務的観点から解説します。
遺産の使い込みとは
遺産の使い込みとは、相続人の一人が被相続人の財産である預貯金をおろしたり財産を勝手に売却したりして得たお金を、無断で自分のために使ってしまうような行為を指します。
使い込みがあった場合の影響:
- 相続財産の減少
- 相続人間のトラブル
- 法的責任(不当利得返還請求や損害賠償請求の可能性)
遺産の使い込みを疑われた場合の対処法
1 相手方の主張をよく吟味して慎重に回答する
- 感情的にならず、冷静に対応する
- 相手の主張内容をよく吟味する
- 放置せずに、対応方針を慎重に検討する
- 必要に応じて早期から弁護士に相談する
十分に検討せずに適当な回答をしてしまった場合で、あとからそれを撤回するような主張をすると、相手方や裁判所から信頼を失い、不利な結果につながることがあります。
2 反論の内容を検討する
使い込みを疑っている他の相続人が提示する可能性のある証拠:
- 被相続人の預貯金口座の取引履歴
- 被相続人の介護記録や病院のカルテ
使い込みを疑われている側は、相手方の具体的な主張や証拠を確認して、事実と違うところについて、できるだけ証拠を示しつつ反論をしていきます。
3 考えられる反論パターン
a) 預貯金の引き出しにはかかわっていない旨の主張
- 証拠の例:
- 金融機関の払戻請求書(被相続人の筆跡であることを示す)
- ATM利用時の防犯カメラ映像(可能であれば)
- 被相続人の行動記録(日記,カレンダーなど)
- 医療記録(被相続人の判断能力を示すもの)
b) 預貯金を引き出したが、被相続人に依頼されてのことである旨の主張
- 証拠の例:
- 被相続人からの依頼メモや手紙
- 電話やメールの記録
- 目撃者の証言(介護ヘルパーなど)
- 財産管理委任契約書(存在する場合)
c) 被相続人の生活や介護の必要費用として引き出した旨の主張
- 証拠の例:
- 領収書や請求書
- 家計簿や支出記録
- 介護サービス利用記録や医療費の明細
- 被相続人の生活状況を示す写真や動画
- ケアマネージャーや医療関係者の証言
d) 被相続人から贈与された旨の主張
- 証拠の例:
- 贈与契約書(存在する場合)
- 被相続人の手紙やメモ
- 目撃者の証言
- 贈与税の申告書類(申告している場合)
- 贈与の事実を示す銀行振込記録
4. 法的観点からの解説
1 民法上の位置づけ
- 不法行為(民法709条)
- – 要件:
故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、これによって損害を加えること - – 効果:
損害賠償責任が発生
- – 要件:
- 不当利得(民法703条)
- – 要件:
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすこと - – 効果:
利得の返還義務が発生
- – 要件:
- 共有物の管理(民法252条)
- – 相続開始後、遺産分割前の相続財産は共有状態にあるとみなされる
- – 共有物の管理は、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する
2 刑事法上の位置づけ
- 横領罪(刑法252条)
- – 要件:他人の物を占有し、これを横領すること
- – 刑罰:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 業務上横領罪(刑法253条)
- – 要件:業務上他人の物を占有し、これを横領すること
- – 刑罰:10年以下の懲役
3 相続法上の影響
- 具体的相続分の修正
- – 遺産の使い込みが認められた場合、使い込んだ相続人の具体的相続分が減少
- – 他の相続人の具体的相続分が増加
- 寄与分の考慮
- – 被相続人の介護等で特別の寄与をした相続人は、寄与分を主張できる(民法904条の2)
- 遺留分侵害
- – 生前贈与や遺贈により遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求が可能(民法1031条)
4 時効の問題
- 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
- – 被害者が損害および加害者を知った時から3年
- – 不法行為の時から20年(民法724条)
- 不当利得返還請求権の消滅時効
- – 権利を行使することができる時から10年(民法166条1項)
- 相続回復請求権の期間制限
- – 相続権侵害の時から5年
- – 相続開始の時から20年(民法884条)
5. 使い込みを疑われないための予防策
- 財産管理の透明化
- – 定期的な収支報告
- – 複数人による確認体制
- – デジタルツールの活用
- 法的手続きの活用
- – 財産管理委任契約の締結
- – 任意後見契約の締結
- – 公正証書遺言の作成
- 専門家の活用
- – 税理士・公認会計士の起用
- – 弁護士によるアドバイス
- – 社会福祉士・ケアマネージャーとの連携
- 家族間のコミュニケーション強化
- – 定期的な家族会議の開催
- – 意思決定プロセスの明確化
- 記録の重要性
- – 詳細な記録の保管
- – 写真・動画による記録
- – 電子データのバックアップ
6. 使い込みの告発を受けた際の初動対応
1 初期対応の重要性
- 告発内容の記録と証拠保全
- – 告発を受けた日時・方法の記録
- – 相手方からの通知や証拠書類の保管
- – 関連する通帳・領収書等の即時保全
- – デジタルデータのバックアップ作成
- コミュニケーション方針の確立
- – 相手方との連絡手段の確定(書面・メール等)
- – 連絡内容の記録保持
- – 感情的な対応の回避
- – 必要に応じた専門家の介入
- 家族関係維持のための配慮
- – 他の親族への適切な情報共有
- – 中立的な立場の親族の協力要請
- – 対話の機会の確保
- – 誠実な対応姿勢の維持
2 専門家への相談
- 相談すべき専門家
- – 弁護士(法的対応)
- – 税理士(税務関係)
- – 公認会計士(財産評価)
- 相談時期の判断
- – 告発直後の早期相談推奨
- – 問題の複雑化前の介入
- – 証拠収集段階からの助言取得
7. 調停・訴訟に発展した場合の対応
1 調停手続きの概要
- 調停の申立て
- – 管轄裁判所の確認
- – 必要書類の準備
- – 申立費用の確認
- 調停での対応
- – 主張・反論の準備
- – 証拠の整理と提出
- – 和解案の検討
2 訴訟対応
- 訴訟提起への準備
- – 訴状への対応方針策定
- – 答弁書の作成
- – 証拠の整理・保全
- 訴訟進行における注意点
- – 期日の厳守
- – 証拠提出のタイミング
- – 和解協議の可能性検討
- 費用関係
- – 弁護士費用の見積り
- – 訴訟費用の予測
- – 和解金の検討
8. 相続税との関係
1 相続税申告への影響
- 使い込み金額の取扱い
- – 相続財産としての計上方法
- – 債権債務関係の整理
- – 評価額の確定方法
- 申告手続きでの注意点
- – 期限内申告の重要性
- – 財産の網羅的な把握
- – 関係者間での情報共有
2 税務調査対応
- 調査準備
- – 資料の整理・保管
- – 取引記録の確認
- – 関係者への事前確認
- 実地調査での対応
- – 正確な説明の準備
- – 追加資料の準備
- – 専門家の同席検討
- 追徴課税リスクへの対応
- – 修正申告の要否判断
- – 加算税等の検討
- – 納税資金の確保
最近の裁判例
1 東京高裁平成30年6月27日判決
事案の概要:
被相続人の預金から約2,000万円の引き出しがあり、同居していた長男が使い込んだとして、他の相続人から不当利得返還請求を受けた事例。
判決のポイント:
長男は被相続人の生活費等に使用したと主張したが,具体的な立証ができず
引き出した金額のほとんどについて不当利得返還請求が認められた
2 大阪高裁平成27年7月9日判決
事案の概要:
被相続人の介護をしていた長女が、預金から継続的に引き出しを行っていたことについて、他の相続人から不当利得返還請求を受けた事例。
判決のポイント:
「社会通念に照らし相当と認められる額」については,領収書がなくても経費として認められた
ただし,高額な引き出しについては具体的な立証が必要とされた
3 最高裁平成29年1月31日判決
事案の概要:
被相続人の子である相続人の1人が、被相続人の生前に高額な贈与を受けていたとして、他の相続人から遺留分減殺請求を受けた事例。
判決のポイント:
生前贈与が遺留分算定の基礎に算入される場合の価額は,原則として贈与時の価額
ただし,著しく不公平な結果となる特段の事情がある場合は例外的に相続開始時の価額
まとめ
遺産の使い込みを疑われた場合の適切な対処法について解説しました。
主なポイントは以下の通りです:
- 冷静に状況を把握し、感情的にならない
- 相手方の主張を正確に理解し、慎重に対応する
- 具体的な証拠を収集し、反論の準備をする
- 必要に応じて専門家(弁護士等)に相談する
- 使い込みを疑われないための予防策を日頃から講じる
遺産の使い込み問題は、相続に関わる複雑な問題の一つです。適切な対応と予防策を講じることで、多くのトラブルを回避し、円滑な相続を実現することが可能です。