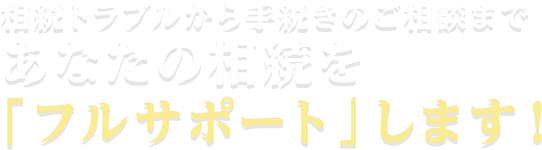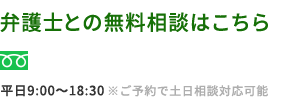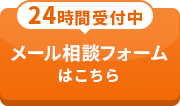遺産分割
依頼者
60代男性
遺産範囲における問題が生じた状況から、円満な遺産分割協議に至るまでの事例
- 亡くなられた方
- 父親、母親
- 相続人
- 長女、長男
- 相続(遺産)
- 不動産、預貯金、現金
ご依頼の背景
依頼者である夫婦は、父母の世話をするために一緒に暮らしていました。ある時、父母が相次いで亡くなり、遺産分割が必要となりました。依頼者は遠方で生活する長女にこれまでの経緯を説明しましたが、長女は依頼者が生前の遺産を引き出していたことから遺産範囲について疑問を持ち、遺産分割が進まない状態となりました。依頼人の主張
依頼者は、長女が感情的であり、訴訟外の話し合いが難しいため、弁護士や裁判所を介して話し合いを進めていくことを希望していました。また、依頼者は、法定相続分に基づいて遺産分割を行いたいという希望を持っていました。サポートの流れ
依頼者は、長女に対して弁護士を代理人として連絡を行い、過去の預金の引き出しに関する資料を可能な限り提出しました。その後、調停を提起し、裁判所を介して遺産分割問題を解決することを目指しました。結果
長女は、最初は納得しようとしなかったものの、依頼者が丁寧に証拠を収集し、開示していくことで次第に状況が変化しました。また、預金の引き出しに関する経緯についても、合理的な理由を示すことができ、長女が納得するまでの説明が出来ました。この結果、依頼者と長女は遺産の範囲について共通の認識を持つことができ、円満な遺産分割協議が実現しました。依頼者が長年父母を献身的に支えてきたことに対して、長女から感謝の言葉が述べられるようになりました。最終的に、双方が法定相続分に基づく遺産分割で合意し、調停が成立しました。
この事例から、遺産分割問題に対する適切な解決策として、弁護士や裁判所を利用することが効果的であり、また、適切な証拠の提出や説明が重要であることがわかります。
その他の解決事例
- 亡くなられた方
- 母
- 相続人
- 長男、長女、次男
- 相続(遺産)
- 預貯金、不動産、車
- 亡くなられた方
- 母
- 相続人
- 夫、長男、長女
- 相続(遺産)
- 預貯金
- 亡くなられた方
- 父、母
- 相続人
- 長女の子2名、長男、養子
- 相続(遺産)
- 不動産
- 亡くなられた方
- 兄弟(兄)
- 相続人
- 長女、長男、次男の子2名、次女、四男
- 相続(遺産)
- 預貯金
- 亡くなられた方
- 義母
- 相続人
- 養子(依頼者)、四男、三男の子(代襲相続人)
- 相続(遺産)
- 不動産、預貯金